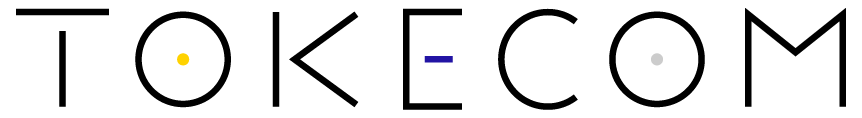◆左から、順に「山形新聞」11月27日、「北海道新聞」11月30日夕刊、「西日本新聞」11月27日夕刊。
新聞と言うと、全国紙の五紙(読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞)の名前くらいは誰でも知っているだろうが、何百万部も出ている日本の全国紙(2015年、概算で、読売新聞912万部、朝日新聞680万部、毎日新聞328万部、日本経済新聞273万部、産経新聞161万部)というのは、世界的に見ても極めて特殊な存在であるということは意外に知られていない。
ヨーロッパでも、米国でも全国で販売されている新聞は少ないし、発行部数も多くはない。ある一定の地域で発行されているのが、地方紙と呼ばれる新聞だが、海外では多くの国で地方紙のほうが発行部数は多いのである。
たとえば、フランスで有名な新聞と言えば、「ル・モンド」とか「フィガロ」という新聞(全国紙)があるが、最大発行部数の新聞は、フランス西部(ブルターニュ地方)で出されている地方紙「ウエスト・フランス」(78万部)である。ドイツでも地方紙のほうが発行部数が多いし、世界的に名前が知られている「フランクフルター・アルゲマイネ」とか、「南ドイツ新聞」も名前からして「地方(地域)」の名前がついている。
米国では、全国紙というと「ウォール・ストリート・ジャーナル」(200万部)[日本版]と「USAトゥディ」(180万部)がある。しかし、世界的に有名なのは「ニューヨーク・タイムズ」とか「ワシントン・ポスト」という地方名のついた地方紙だし、各地域で圧倒的に読まれているのは地方紙のほうである。
さて、日本には、全国紙のほかに、ブロック紙と呼ばれる領域をまたがって読まれている新聞がある。ブロック紙は、三紙(北海道新聞、中日新聞、西日本(にしにっぽん)新聞)が知られているが、中日新聞東京本社発行の「東京新聞」、宮城県(東北地方)の「河北(かほく)新報」、広島県(中国地方)の「中国新聞」もブロック紙に含める場合も多い。
そして県ごとに出されているのが県紙である。発行エリアが一府県の全域にわたる新聞を指す。多くは第二次世界大戦下の「一県一紙」統制時に多数の新聞を統合してその県の唯一の地元紙として成立した新聞である。
地方紙は、全国紙のように全国各地域に支社が置かれているわけではないので、全国ニュースや芸能情報、文化情報は、ニュース配信の通信社(共同通信社、時事通信社)の配信記事を利用している。記事を利用しても記事の「見出し」や掲載方法は、それぞれの新聞が独自に行っている。そこにある意味で地方紙の独自性がうかがわれるのである。
今回、なぜこのような話をしたかといえば、先月末から今月初めに私の執筆した「原節子・追悼」原稿が、共同通信文化部を通じて地方紙に配信され掲載されたからだ。共同通信から掲載紙がまとめて送られてきて、あらためて各紙の掲載記事を見ていて、非常に興味深かった。むろん、配信通り(「原節子が表現したもの 『一人でいる自由』貫く」)に「見出し」を使っているところ(写真左=山形新聞、同右=西日本新聞)が多いのだが、独自の「見出し」を使っている新聞があって、「なるほど」と思わされたのである。
たとえば、「北海道新聞」の見出しは(写真中央)、「運命への『拒否』貫く 伝説の女優・原節子を悼む」となっているし、「神戸新聞」の見出しは「運命を拒否する強い意志」、「山梨日日新聞」は「運命への『拒否』を体現」、「東奥日報」は「『一人の自由』貫く 原節子さんを悼む」、「京都新聞」は「女が一人でいる自由貫く」、「信濃毎日新聞」は「『自由』貫き『伝説』に」となっている。地方紙それぞれの記者が、配信記事にも独自性を持たせようとしている意識がうかがえて、非常に面白かった。
今や、全国紙は均質な報道ばかりで、面白みもなく独自性もないが、地方紙は、独自の立場から誇り高く屹立している感じがするこのごろである。
今や、全国紙は均質な報道ばかりで、面白みもなく独自性もないが、地方紙は、独自の立場から誇り高く屹立している感じがするこのごろである。
桜井哲夫