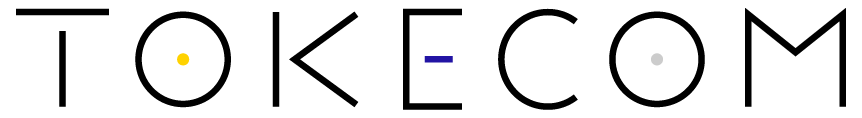▼2016年5月
◎本橋哲也『宮城聰の演劇世界-孤独と向き合う力』(塚本知佳との共著)青弓社
著者の一言 30年以上にわたる演出家、宮城聰の仕事を、本人や役者、スタッフのインタビューを交えながら、代表舞台作品を詳細に論じることで観照しました。
2017/02/27
2017/02/20
教員の新近刊
トケコミ教員の今年度刊、近刊をご紹介しましょう。
▼2016年4月
◎本橋哲也『ディズニー・プリンセスのゆくえ-白雪姫からマレフィセントまで』ナカニシヤ出版
著者の一言 20世紀の古典的なディズニー・プリンセス映画の再検証から始めて、21世紀の革命的な諸作品を徹底的に解読しました。
▼2016年6月
◎柴内康文「ソーシャルキャピタル・メディア・格差」(佐藤卓己 編)『デジタル情報社会の未来』(岩波講座 現代 第9巻)pp.43-65. 岩波書店
著者の一言 岩波書店が出している『講座 現代』というシリーズの一冊の中の一つ、です。
『講座 現代』が前回に出たのは1963-64年なのだそうで、50年ぶりの刊行です。50年とは言わないが、ある程度読み継がれるものを(すぐに古くならないものを)と要望されたのですが、「ネットと人間関係」で書くことになっていた私は、それで大変に悩むことになりました。少しはそういうものになっていればいいのですが。
▼2016年7月
◎西垣 通『ビッグデータと人工知能-可能性と罠を見極める』中央公論新社(中公新書)
著者の一言「AI狂騒から離れて人間の知性を鍛えるために」と帯の惹句にありますが、ともかく老骨に鞭打って一生懸命書きました。どなたにも読めるやさしい本です。
◎北村 智・佐々木裕一・河井大介『ツイッターの心理学-情報環境と利用者行動』
誠信書房
日本でいまツイッターとどう向き合うべきかが分かりやすく解説されている初の専門書。
▼2016年8月
◎北村 智「情報行動における年齢・時代・世代効果の検討」ほか『日本人の情報行動 2015』(橋元良明編)東京大学出版会
日本人のメディア利用行動やコミュニケーション行動について、厳密な社会統計学的な方法論に基づいた調査により、メディア環境の大変動を詳細な数値として明快に示す。2015年版では、新たにLINE、facebook、twitterなどのソーシャルメディアや動画サイトの利用実態の貴重な統計を多数収録。
▼2017年3月(予定)
◎ロバート・D・パットナム(柴内康文訳)『われらの子ども』創元社
著者の一言 同じ著者の『孤独なボウリング』を以前翻訳したことがあり、その続編的意味合いも持つ本をもう一度手がけました。「格差社会」と言われますが、本書は特にアメリカの若者に焦点を当て、彼らの生きる世界にどのような格差が発生しているのかをインタビューとデータ分析で追います。アメリカの若者のさまざまな暮らしぶりを垣間見ることもできるでしょう。例えば大学受験の激しさから、時間を削って試験の点数競争に追われている、それもあまり知られていないアメリカの若者の(一つの)姿です。
▼2017年4, 5月
◎松永智子(共著)『いのちのふるさと海といきる』(田中 克・下村奈津子 編)昭和堂
著者の一言 学生時代、農学部開講の授業であった気仙沼・舞根湾合宿に参加し、漁師さんの植林活動「森は海の恋人」に魅せられました。そのときのご縁で、里山と川、海の「つながり」について考えたり、ときどき書いたりしています。多様な執筆者10名の集うこの本に、ハワイの日本人移民と海とのつながりに光をあてた「行き交う人のふるさと」という文章を寄せました。
▼2016年4月
◎本橋哲也『ディズニー・プリンセスのゆくえ-白雪姫からマレフィセントまで』ナカニシヤ出版
著者の一言 20世紀の古典的なディズニー・プリンセス映画の再検証から始めて、21世紀の革命的な諸作品を徹底的に解読しました。
▼2016年6月
◎柴内康文「ソーシャルキャピタル・メディア・格差」(佐藤卓己 編)『デジタル情報社会の未来』(岩波講座 現代 第9巻)pp.43-65. 岩波書店
著者の一言 岩波書店が出している『講座 現代』というシリーズの一冊の中の一つ、です。
『講座 現代』が前回に出たのは1963-64年なのだそうで、50年ぶりの刊行です。50年とは言わないが、ある程度読み継がれるものを(すぐに古くならないものを)と要望されたのですが、「ネットと人間関係」で書くことになっていた私は、それで大変に悩むことになりました。少しはそういうものになっていればいいのですが。
▼2016年7月
◎西垣 通『ビッグデータと人工知能-可能性と罠を見極める』中央公論新社(中公新書)
著者の一言「AI狂騒から離れて人間の知性を鍛えるために」と帯の惹句にありますが、ともかく老骨に鞭打って一生懸命書きました。どなたにも読めるやさしい本です。
◎北村 智・佐々木裕一・河井大介『ツイッターの心理学-情報環境と利用者行動』
誠信書房
日本でいまツイッターとどう向き合うべきかが分かりやすく解説されている初の専門書。
▼2016年8月
◎北村 智「情報行動における年齢・時代・世代効果の検討」ほか『日本人の情報行動 2015』(橋元良明編)東京大学出版会
日本人のメディア利用行動やコミュニケーション行動について、厳密な社会統計学的な方法論に基づいた調査により、メディア環境の大変動を詳細な数値として明快に示す。2015年版では、新たにLINE、facebook、twitterなどのソーシャルメディアや動画サイトの利用実態の貴重な統計を多数収録。
▼2017年3月(予定)
◎ロバート・D・パットナム(柴内康文訳)『われらの子ども』創元社
著者の一言 同じ著者の『孤独なボウリング』を以前翻訳したことがあり、その続編的意味合いも持つ本をもう一度手がけました。「格差社会」と言われますが、本書は特にアメリカの若者に焦点を当て、彼らの生きる世界にどのような格差が発生しているのかをインタビューとデータ分析で追います。アメリカの若者のさまざまな暮らしぶりを垣間見ることもできるでしょう。例えば大学受験の激しさから、時間を削って試験の点数競争に追われている、それもあまり知られていないアメリカの若者の(一つの)姿です。
▼2017年4, 5月
◎松永智子(共著)『いのちのふるさと海といきる』(田中 克・下村奈津子 編)昭和堂
著者の一言 学生時代、農学部開講の授業であった気仙沼・舞根湾合宿に参加し、漁師さんの植林活動「森は海の恋人」に魅せられました。そのときのご縁で、里山と川、海の「つながり」について考えたり、ときどき書いたりしています。多様な執筆者10名の集うこの本に、ハワイの日本人移民と海とのつながりに光をあてた「行き交う人のふるさと」という文章を寄せました。
2017/02/14
近刊情報『われらの子ども」
Putnamの新刊、Our Kidsが柴内先生の訳『われらの子ども』で出ます。刊行は3/23の予定です。
『われらの子ども:米国における機会格差の拡大』
ロバート・D・パットナム(柴内康文訳)創元社
没落する中産階級を子どもの成長を通して描く、トランプ以後のアメリカ社会論。子どもたちにはもう、平等な成功のチャンスはない!
 トランプ勝利の背景を抉り出し、日本の近未来をも占う、汎用性の高い戦慄の格差社会論(出版元の紹介文から)。
トランプ勝利の背景を抉り出し、日本の近未来をも占う、汎用性の高い戦慄の格差社会論(出版元の紹介文から)。
参考記事(「朝日新聞」2016年9月6日付け)
「(インタビュー)格差が深める米の分断 米国社会の変質を分析する社会学者、ロバート・パットナムさん」
■
子どもはすべからく「われらの子ども」。あの子も、この子も、ひとしく「われらの子ども」、今後の社会をになう大事な存在。教育機会も含め、かれらの成育を社会で保障すること。それは最低限、大人がしなければならないことです。学校教育の受益者は、まずは子ども本人、そして結局は社会なのですから。
本書のゲラを柴内先生にチラッと見せてもらいました。読みやすい翻訳です。原著はナラティブ(語り)が多いため、その分スラングも多く使われています。それだけでも訳出には苦労されたのではないでしょうか。
下側に置いた写真は原著のカバーです。モノクロの殺伐としたブランコはインパクトがあります。さて訳書の表紙は何でしょう?
『われらの子ども:米国における機会格差の拡大』
ロバート・D・パットナム(柴内康文訳)創元社
没落する中産階級を子どもの成長を通して描く、トランプ以後のアメリカ社会論。子どもたちにはもう、平等な成功のチャンスはない!
 トランプ勝利の背景を抉り出し、日本の近未来をも占う、汎用性の高い戦慄の格差社会論(出版元の紹介文から)。
トランプ勝利の背景を抉り出し、日本の近未来をも占う、汎用性の高い戦慄の格差社会論(出版元の紹介文から)。参考記事(「朝日新聞」2016年9月6日付け)
「(インタビュー)格差が深める米の分断 米国社会の変質を分析する社会学者、ロバート・パットナムさん」
■
本書のゲラを柴内先生にチラッと見せてもらいました。読みやすい翻訳です。原著はナラティブ(語り)が多いため、その分スラングも多く使われています。それだけでも訳出には苦労されたのではないでしょうか。
下側に置いた写真は原著のカバーです。モノクロの殺伐としたブランコはインパクトがあります。さて訳書の表紙は何でしょう?
(川浦康至)
2017/02/08
清水きよし舞台写真展、2/11まで
 |
| 【坂野正人 撮影】 |
彼の舞台を35年(も)撮り続けてきた坂野正人さんの写真展が駿河台で開催中です。
出会いは多分福生。私はしばらく米軍基地のそばに住んでいました。坂野さんは、福生の米軍払い下げ住宅に住む人たちの写真集『トーキング・アバウト・フッサ』を出版、それを見せていただいたのがお付き合いの始まり、と清水さん。
写真展は11日まで毎日、12時から19時まで。10、11はマイム&トーク&演奏も。
会場のESPACE BIBLIO(エスパスビブリオ)はブックカフェ。巨大な本、ユニークな品揃えに圧倒されます。御茶ノ水駅から会場までの道には文化学院の建物もあり、洒落た一角にあります。
清水さんご自身は50年の舞台生活、つい先日70歳を迎えられました。今年は11月まで、全国でマイム生活50周年記念公演が組まれています。東京各地、瀬戸、八戸、大阪、名古屋、博多、八尾、松江と、みなさんの近くにも。
2017/02/03
【学問のミカタ】ルールブックにない“ルール”
〈コーチング論〉担当の遠藤愛です.
2月のテーマは「ルール」.今回私がご紹介するルールは,ルールブックにのっていない“ルール”です.
スポーツと運動の違いに,競技性とともにルールの存在が挙げられます.
他のスポーツ同様,私が専門とするテニスにおいても,毎年少しずつルールは修正され,選手はルールを理解し,あるときは従い,あるときはそれを使います.
かつて悪童と呼ばれたアメリカのスーパースター,ジョン・マッケンローが,1試合の中で2回のwarning* の後に3回目で失格となっていたルールが,1回のwarning後にいきなり失格となるルールへと改正されたのを知らずに失格となってしまったのは有名な話です.
マッケンローはルールを知り尽くし,ルール違反ギリギリのところで心理戦を仕掛けてくる,そんなプレーヤーでもあったと言うとマッケンローファンには叱られるでしょうか.
私自身の経験を振り返ると,高校生の時にプロに混じって試合に出るようになった最初の頃に,今となっては笑い話のエピソードがあります.
テニスの試合では,選手が試合前にネットを挟んでトスを行い,サービス,レシーブ,そしてプレーするサイドを選択する権利を決めます.当時,高校生だった私は日本のトップランカーとの対戦で少し緊張していたようです.相手がトスに勝ってサービスを選択した後,私は「レシーブ!」と言い,対戦相手であったプロの先輩は「では,サイドはこちら」と言って試合が始まりました.
私はずっと「何かおかしいなあ……」という気持ちのままプレーして,結局は完敗してしまいました.今でも学生にテニスのルールを説明する際に披露するエピソードです.お分かりになりますか?
そうです.サービスを相手が選択した時点で自動的にレシーブは決まっているので,対戦相手はまんまとサービスとプレーするサイドの両方を得たという訳です.彼女はルールに反したわけではなく,試合後,父にも「お前はアホか」と叱られましたが,私は「プロの世界ってこういうことなのか.教えてくれないんだ〜」とちょっと寂しくなったのを今でも覚えています.
しかし,さすがに多くの観客が注目する世界レベルのトーナメントではちょっと違いました.世界レベルでプレーする選手たちは自負を持ってプレーしています.テニスもまた世界共通のルールに則って粛々と進行していくスポーツです.
私が一番大切にしなくてはならないと小さな時からたたき込まれたこと,そして,今も大切にと指導しているのは相手,用具,そして競技に対する愛情と敬意を持つことです.
実は,自分がプロフェッショナルになったということを一番強く実感したのは,初勝利をあげた時でも,初めて賞金を受け取った時でもありません.世界レベルのプレーヤーたちと戦い,相手から敬意を持って迎えられた時なのです.
プロとして世界ツアーを回るようになり,オーストラリア,ブリスベンの大会でトップ20の選手に初めて勝ったとき,敗者であるはずの彼女がまっすぐ私の顔を見て「Well play」と勝者である私のプレーを賞讃してくれました.咄嗟に,勝者である私も「Good match」と応じて,「お互いにベストを尽くしたよね,よい試合したよね」という意味を込めて強く握手をしました.
他の競技でも見られますが,ルールとして明確に記されてはいないけれど,プレー後にお互いをたたえ合う姿が私はとても好きです.
この他にも,プレー中にフレームショットやネットインで相手のコートに入り,運よくポイントを取ってしまったときは「ちょっとごめんね」の意味を持ってラケットをかざします.新しいボールになったときは「今からニューボールで打つよ」と相手にボールを高く掲げてプレーを始める前に必ず見せます.これらのことは,正々堂々と戦うということなのだと私は理解し,この後,自分が日本国内で若手とプレーする時に試合の中で実践しながら伝えたつもりです.
ルールブックには載っていないけれど,多くのプレーヤーが実践すること,その中で私が特に好きなのは,決勝戦を戦った後の表彰式での選手たちのスピーチです.
大会スタッフからスポンサーの名前が書かれたメモを渡されることもあり,スポンサー,運営スタッフへの感謝は必ず言いますが,それ以外は選手が思うままに勝負の後の心境を語ります.そのとき,ほとんどの選手が最初に,共に戦った相手を「Congratulation……」とたたえます.これらは誰かから教えられたのではなく,トッププレーヤーの姿勢を見て自ら学び,そして,試合後に自然にわき上がって来る本当の気持ちでした.
試合後のスピーチの名場面はYouTubeにもたくさんアップされています.私のオススメは2009年全豪オープン男子決勝のフェデラーとナダル,2012,2013年ウインブルドン男子決勝でのマレーとフェデラーです.彼らのスピーチは,激闘後とは思えないくらい優しく,切なくなります.
今はさまざまなスポーツをテレビやネットで見ることができます.彼らの優れたプレーや激しいバトルももちろん魅力的ですが,お互いを尊重し合う選手同士のやりとりにもまた注目して下さい.トッププレーヤーのスピーチ力,表現力もまた素晴らしいものです.
--------------
*warning:警告.審判が選手のルール違反に対して発する警告.遅延行為,相手を侮辱する行為,試合中のルールに反するコーチングなどさまざまな行為が定められている.
【学問のミカタ】2月のテーマは「ルール」
2月のテーマは「ルール」.今回私がご紹介するルールは,ルールブックにのっていない“ルール”です.
スポーツと運動の違いに,競技性とともにルールの存在が挙げられます.
他のスポーツ同様,私が専門とするテニスにおいても,毎年少しずつルールは修正され,選手はルールを理解し,あるときは従い,あるときはそれを使います.
かつて悪童と呼ばれたアメリカのスーパースター,ジョン・マッケンローが,1試合の中で2回のwarning* の後に3回目で失格となっていたルールが,1回のwarning後にいきなり失格となるルールへと改正されたのを知らずに失格となってしまったのは有名な話です.
マッケンローはルールを知り尽くし,ルール違反ギリギリのところで心理戦を仕掛けてくる,そんなプレーヤーでもあったと言うとマッケンローファンには叱られるでしょうか.
私自身の経験を振り返ると,高校生の時にプロに混じって試合に出るようになった最初の頃に,今となっては笑い話のエピソードがあります.
テニスの試合では,選手が試合前にネットを挟んでトスを行い,サービス,レシーブ,そしてプレーするサイドを選択する権利を決めます.当時,高校生だった私は日本のトップランカーとの対戦で少し緊張していたようです.相手がトスに勝ってサービスを選択した後,私は「レシーブ!」と言い,対戦相手であったプロの先輩は「では,サイドはこちら」と言って試合が始まりました.
私はずっと「何かおかしいなあ……」という気持ちのままプレーして,結局は完敗してしまいました.今でも学生にテニスのルールを説明する際に披露するエピソードです.お分かりになりますか?
そうです.サービスを相手が選択した時点で自動的にレシーブは決まっているので,対戦相手はまんまとサービスとプレーするサイドの両方を得たという訳です.彼女はルールに反したわけではなく,試合後,父にも「お前はアホか」と叱られましたが,私は「プロの世界ってこういうことなのか.教えてくれないんだ〜」とちょっと寂しくなったのを今でも覚えています.
しかし,さすがに多くの観客が注目する世界レベルのトーナメントではちょっと違いました.世界レベルでプレーする選手たちは自負を持ってプレーしています.テニスもまた世界共通のルールに則って粛々と進行していくスポーツです.
私が一番大切にしなくてはならないと小さな時からたたき込まれたこと,そして,今も大切にと指導しているのは相手,用具,そして競技に対する愛情と敬意を持つことです.
実は,自分がプロフェッショナルになったということを一番強く実感したのは,初勝利をあげた時でも,初めて賞金を受け取った時でもありません.世界レベルのプレーヤーたちと戦い,相手から敬意を持って迎えられた時なのです.
プロとして世界ツアーを回るようになり,オーストラリア,ブリスベンの大会でトップ20の選手に初めて勝ったとき,敗者であるはずの彼女がまっすぐ私の顔を見て「Well play」と勝者である私のプレーを賞讃してくれました.咄嗟に,勝者である私も「Good match」と応じて,「お互いにベストを尽くしたよね,よい試合したよね」という意味を込めて強く握手をしました.
他の競技でも見られますが,ルールとして明確に記されてはいないけれど,プレー後にお互いをたたえ合う姿が私はとても好きです.
この他にも,プレー中にフレームショットやネットインで相手のコートに入り,運よくポイントを取ってしまったときは「ちょっとごめんね」の意味を持ってラケットをかざします.新しいボールになったときは「今からニューボールで打つよ」と相手にボールを高く掲げてプレーを始める前に必ず見せます.これらのことは,正々堂々と戦うということなのだと私は理解し,この後,自分が日本国内で若手とプレーする時に試合の中で実践しながら伝えたつもりです.
ルールブックには載っていないけれど,多くのプレーヤーが実践すること,その中で私が特に好きなのは,決勝戦を戦った後の表彰式での選手たちのスピーチです.
大会スタッフからスポンサーの名前が書かれたメモを渡されることもあり,スポンサー,運営スタッフへの感謝は必ず言いますが,それ以外は選手が思うままに勝負の後の心境を語ります.そのとき,ほとんどの選手が最初に,共に戦った相手を「Congratulation……」とたたえます.これらは誰かから教えられたのではなく,トッププレーヤーの姿勢を見て自ら学び,そして,試合後に自然にわき上がって来る本当の気持ちでした.
試合後のスピーチの名場面はYouTubeにもたくさんアップされています.私のオススメは2009年全豪オープン男子決勝のフェデラーとナダル,2012,2013年ウインブルドン男子決勝でのマレーとフェデラーです.彼らのスピーチは,激闘後とは思えないくらい優しく,切なくなります.
今はさまざまなスポーツをテレビやネットで見ることができます.彼らの優れたプレーや激しいバトルももちろん魅力的ですが,お互いを尊重し合う選手同士のやりとりにもまた注目して下さい.トッププレーヤーのスピーチ力,表現力もまた素晴らしいものです.
--------------
*warning:警告.審判が選手のルール違反に対して発する警告.遅延行為,相手を侮辱する行為,試合中のルールに反するコーチングなどさまざまな行為が定められている.
【学問のミカタ】2月のテーマは「ルール」
- 経済学部 経済学とルールの関係性
- 経営学部 実際の特長を広告で表現できない?!
- 現代法学部 法も「ルール」~そんな「法」の学び方をお教えしましょう~
- 全学共通教育センター 英語学習のルール?
登録:
コメント (Atom)