学問のミカタ、今回の担当はカルチュラル・スタディーズ、英米文学、英米文化論担当の本橋先生です。
「カニバリズム=食人」と聞くと、皆さんはどのようなことを思い浮かべられますか?人類が忌避してきたタブー?飢餓を救う道がない緊急状態で行われる生存手段?「野蛮人」の風習としてヨーロッパの植民者たちが先住民に押し付けた人種差別のレッテル?アジア太平洋戦争中に食糧補給のない日本軍兵士が行ったこと?中国などでグルメの極致として洗練されてきた技巧?・・・
いずれにしろ、カニバリズムは肉食動物である人類にとって、実はきわめて身近に行われてきたことであって、必ずしも私たちにとって疎遠なものではありません。たとえば、私たちは「食べてしまいたいほど好きだ」などと言うことがありますが、それは性愛と食欲が深く関わっているからでしょう。皆さんの中にも愛読者がおられるでしょうが、宮沢賢治やアーシュラ・ル=グインといった作家の作品では、カニバリズムが重要なテーマの一つとなっていますし、「赤ずきん」とか「ヘンゼルとグレーテル」といったおとぎ話の中心にもカニバリズムがありますね。「人を食う話」は人間にとって近しいものである、というか、あまりに身近なものであるだけに、できれば遠ざけておきたい、ものであるわけです。
このようなカニバリズムの実態に学問的に迫るためには、その発現形態を分析するだけでなく、それが言語によって表象されてきた歴史を探求することが肝心です。私なりにカニバリズム言説の歴史を整理すると以下のようになります。
第一期は古代ギリシャから中世まで、ヘロドトスやマンデヴィル、マルコ=ポーロといった作家が有名ですが、食人が理解不能な他者の習慣として描かれており、そのような怪物的存在は自己の共同体の外部を示すために必要なだけで、実在を証明する必要はありませんでした。それが第二期の西洋植民地主義の時代になると、コロンブスがたまたま耳にした「カニバレス」という音から「食人種」が実体化されたように、記号による被植民者の悪魔化の手段として伝播します。この傾向はアメリカ新大陸から太平洋の島々、オーストラリア、東南アジア、アフリカにまで植民地支配とともに拡充してゆき、モンテーニュやスウィフト、サドといった稀有な文化相対主義者もいたのですが、植民地主義者が自己を正当化し、他者を周縁化する力学のもとに、植民地支配が免罪される契機が作られていきました。第三期は二〇世紀のポストコロニアル時代における修正主義的な知の積み重ねによって、以前のヨーロッパ中心主義的なカニバリズム言説の歪みが検証されていきます。アレンズやオベイセーカラといった学者たちの研究によって、先住民による食人慣行に疑問が投げつけられました。たしかにここでベクトルの方向は、コロニアリズムの時代とは逆で、ヨーロッパ中心主義が暴かれていくことになったのですが、自己と他者、ヨーロッパと非ヨーロッパという関係そのものは温存されていました。それが第四期になると、表象の重要性に焦点が当てられ、幻影によって生み出される自己と他者関係の変容が焦点となります。人間と動物とを区別せず、あらゆるモノ自体の自律性に注目するという、先住民の思考に着目しながら、ヨーロッパ人の残した食人儀礼の記録が読み直されていきます。たとえばヴィヴェイロス・デ・カストロが論じるカニバリズムは、自然の身体としての人格である肉を食するという行為において、自然と文化の境界線に位置するものです。食人は「敵」という根源的な他者に対する復讐であると同時に信頼であり、人間だけでなく動物や死者、モノにまでいたる多元的な世界における非ヨーロッパ的で双方向的な「アンチ・ナルシス」の思考を導き出すとされるのです。
食べることは交わることと殺すことと並んで最も人間的で双方向的な行為であって、食事の極限にあるカニバリズムは究極的な信頼の創造とも言えます。カニバリズムという視点から、食と性、神話と歴史、自己と他者、生命と死、信頼と危険といった相互依存概念を考察することが、魅力ある学問的探究である理由もそこにあるのです。
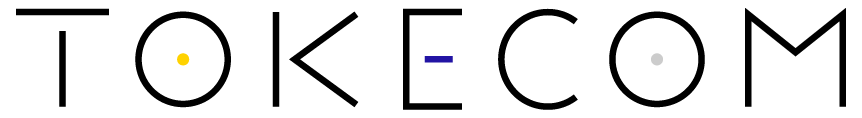
1 件のコメント:
私自身が、現在カニバリズムを抑えるために精神科に通っています。
勿論、食人への欲を抑えるのはとても辛いです。
仕方ないので自分の血液や肉片を食べて抑えてるに過ぎませんが。。。
この話しを出来る方を探しています。
コメントを投稿